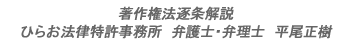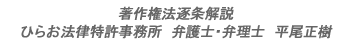| 著作物の種類 |
判 例 |
| 言語著作物 |
【利益額を損害額としたもの】
用字苑事件、アメリカ語要語集事件、戦士の記録事件、SMAP事件、ふぃーるどわーく多摩事件
【受けるべき金銭相当額を基準としたもの】
アニメーションスクール事件、日照権事件、地のさざめごと事件、国文法副読本事件、医師国家試験問題解説事件、住宅デザイン原図集事件、妻たちはガラスの靴を脱ぐ事件、ぐうたら健康法事件、三島由紀夫-剣と寒紅事件、音楽って何?事件、国語テスト事件、転職情報事件
【その他】
医学部助手論文事件、もうひとつのヒロシマ事件、豊後の石風呂事件、民青の告白事件、B市史事件、魔術師三原脩と西鉄ライオンズ事件 |
|
音楽著作物 |
処女林事件、ナニワ観光事件、グッドバイキャロル事件、中部観光事件、にほんの館事件、クラブ・キャッツアイ事件、あぽろン事件、音楽ファイル交換事件3 |
| 舞踊又は無言劇の著作物 |
舞踊振付事件 |
| 美術著作物 |
【利益額を損害額としたもの】
仏壇彫刻事件、Tシャツ図案事件
【受けるべき金銭相当額を基準としたもの】
たいやき君事件、スヌーピー事件、サザエさん事件、昆虫挿絵事件、原色動物大図鑑挿絵事件、日野市壁画事件、動書書体事件、英国のスポーツカー事件、レオナール・フジタ事件、ポパイ事件4、ポパイ事件5、飛騨素描画事件、おむすびパッケージ事件、パンシロン事件、江戸商売図絵事件、角川ミニ文庫事件、武富士事件、浮世絵模写事件1、漫画無料ダウンロード事件
【その他】
レジャー施設パンフレット事件、名産品化粧箱事件、袋帯図柄事件、木目化粧箱事件、恐竜イラスト事件 |
| 地図・図形著作物 |
パリ市鳥瞰図事件、土地宝典事件、きたむら建築設計事件、小林ビル設計図書事件、舞台装置設計図事件 |
| 映画著作物 |
おらが国さを訪ねて事件、パックマン事件2、苦菜花事件、SL世界の車窓事件 |
| 写真著作物 |
パロディー事件、コルトン用写真事件、スイカ写真事件、デンバー元領事写真無断放映事件、商品写真無断掲載事件、東京アウトサイダーズ事件 |
| プログラム著作物 |
在庫管理プログラム事件、ゾーンアナライザシステム事件、ときめきメモリアル事件2、プログラム社内複製事件1、プログラム社内複製事件2、ハニックデータサービス事件、NEW増田足事件 |